僕がいつも感じるのは、
人は、何でもボリュームに対して過剰に価値を置いていること。
逆に、ボリュームが少ないとそれだけで不満の声が多くなる傾向にある。
飲食では、量より質を重視する人が多いが、特に教育に関してはまだまだ「量」重視の人が多いように感じる。
自分のためになりそうなものを一つ得ること
例えば僕は本を読むとき、
「 自分のためになりそうな思考法を一つ得ること」だけにフォーカスする。
求めているのは「思考法」であり、知識量を増やそうといったいわゆる情報弱者の意識は捨てる。
また「一つ」に絞るというスタンスなので、読み始めて数ページで新たな思考法を発見した場合、その先は読まずにいったんその本は本棚に戻す。
むしろ、その「一つの思考法」を深く掘り下げるための自分の時間を確保する。
100の知識(情報)を得ることよりも、たったひとつの成果に繋がる思考法をみいだすことに神経を研ぎ澄ます。
数ある抽象度の高い知識の中で、たったひとつだけでも自分に応用できる「思考法」を得ることができれば十分。
単に知識欲を満たすために「100の情報を得る」のではなく、結果に繋がるために「1つの応用力を得る」というスタンスこそ、「大人の学び方」。
この苦しさに向き合い続けることへの慣れが、自身の抽象思考力を高めることに直結する。
抽象度の高い知識を学んだ、とする。それらの思考パターンをどう応用しうれば、求めている結果を得られるのか?ゴールから逆算しつつ考えていく。
僕たちは何かの学校を卒業するために、全てを暗記してテストに備えているわけではない。
あるいは、新しい世界観を知って「へぇ~!こういうことなんだ!」と知識欲が満たされる快楽だけに溺れて、自分だけのカタルシスを得ることを目的にもしていない。
知識そのものではなく、その思考パターンをどのように解釈し、どのように自分の人生に応用するか。
腑に落ちるまで自分の頭で考えて考えて考え尽くす。「もしかして、これってこういうことなんじゃないか?」という仮説が出るまで、、、
何時間も思考すれば、思考疲れで立ち上がれなかったり、すぐに言葉が出なかったり、吐き気を覚えたりすることもある。
ありがとうございました。
ホンダ
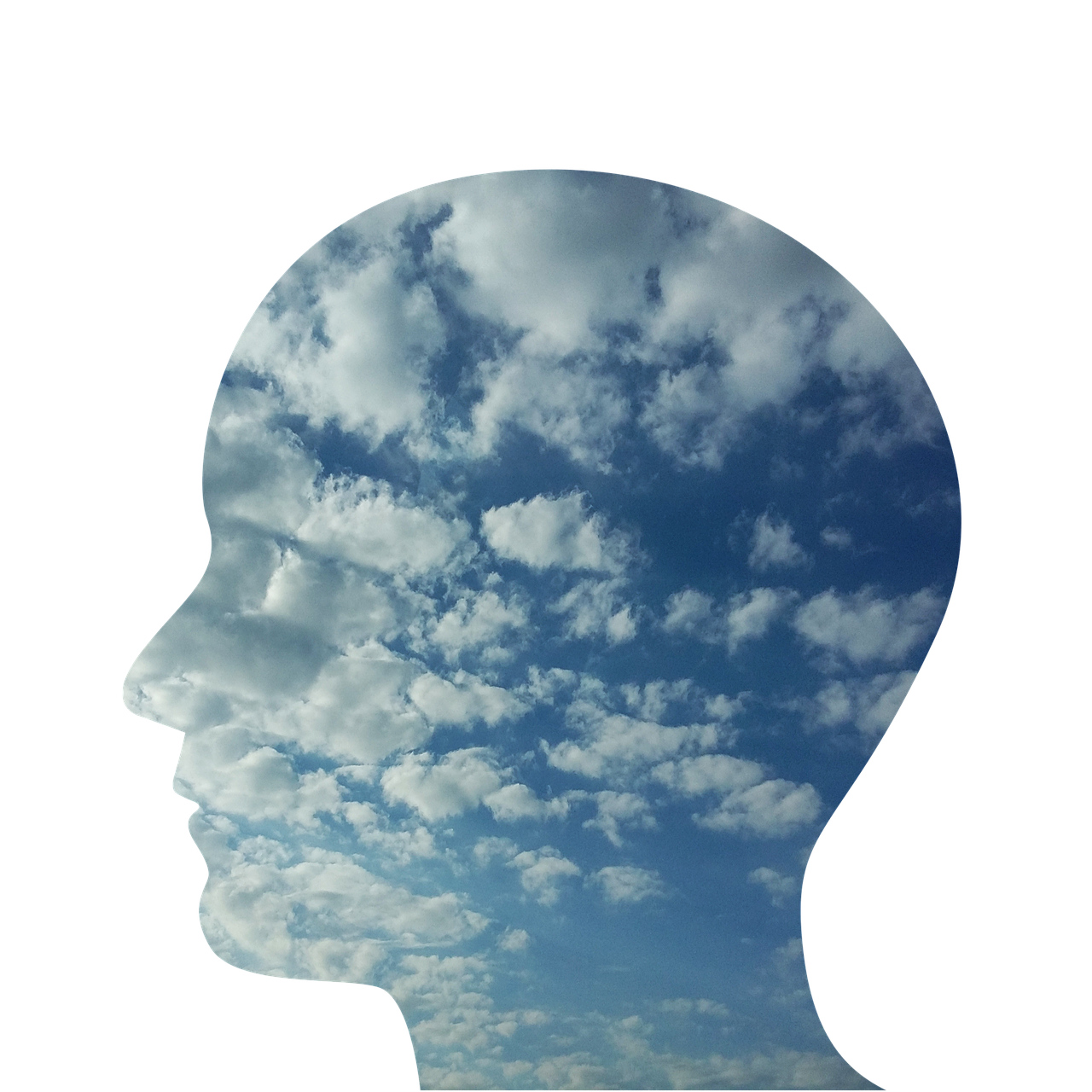


コメント